

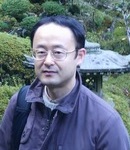
かむろ会の皆様
皆様お変わりございませんか?
この1年、いろいろ調べて新たにわかった私の先祖のことや当時の沖家室のことを、時代を遡って何回かに分けて投稿させていただこうと思います。
以前投稿しました内容を修正しなければならない部分もありますが、その点はお許しください。
私の曽祖父・友澤伊助は明治6年、外入村の野口平八の次男として生を受けました。そして明治13年3月、沖家室友澤家の八代彦七の未亡人・モトが亡くなったその日に十代目として養子に入りました。明治11年に二宮家に転出していた九代目の九八により養育されたものと思われます。
東和町誌によりますと、平八は明治5年頃に外入村の畔頭(くろがしら:庄屋の補佐役)を務めていたようです。
なぜ伊助が友澤の跡取りに選ばれたのか、それは伊助が友澤の血を引いていたから、と考えるのが最も自然です。伊助が友澤の血を引いていたとすれば、実父の平八か実母のどちらかが友澤の血を引く人物だったということになります。もし平八が九八の弟、つまり八代彦七の息子であり、野口家へ養子入りしていたのであれば、その息子である伊助は九八の甥だったことになります。「九八」と「平八」という名前は似ていないこともなく、「平八」という名前は野口家に所縁のある名前とは思えません。また伊助の実母については全く不明ですが、八代彦七の娘が野口平八に嫁ぎ、その息子すなわち外孫が伊助だったという可能性もあります。
私は野口家の菩提寺に、実の高祖父である野口平八について問い合わせました。するとご住職が平八が明治13年1月に亡くなったことを教えてくださいました。つまり伊助は実父が亡くなってすぐに友澤家の養子に入ったことがわかります。当時7歳の伊助にとってどれほど心細かったことか、想像に難くありません。
ご住職によりますと、野口家の末裔の方が私が手紙を送る少し前に亡くなられ、外入にはもう野口家の過去のことを知る方がおられなくなってしまったとのことでした。ですので平八についてのさらなる情報は今のところ得られていません。
「尼崎市史 第六巻」に、明治28年9月の沖家室の生け簀業者として柳原兵左衛門、青木勘五郎とともに伊助の名が記載されています。また以前投稿しましたように、防長紳士録(明治34年6月、防長新聞社)に、「大島郡水産業組合 副組合長 安下庄村 友澤伊助」との記載があるようです。明治33年に実質的な養父である二宮九八が亡くなったのは安下庄の病院ですので、この数年前に伊助共々沖家室から安下庄に移り住んでいたのかもしれません。また明治34年は当時の漁業法が初めて施行された年ですが、伊助が神戸に出てきたのはこの頃です。沖家室で生け簀業を代々営み、大島郡水産業組合の副組合長まで務めながら、その家業に見切りを付けて父祖伝来の地を離れたことになります。この漁業法の施行が家業の妨げになるとの判断があったのかもしれません。